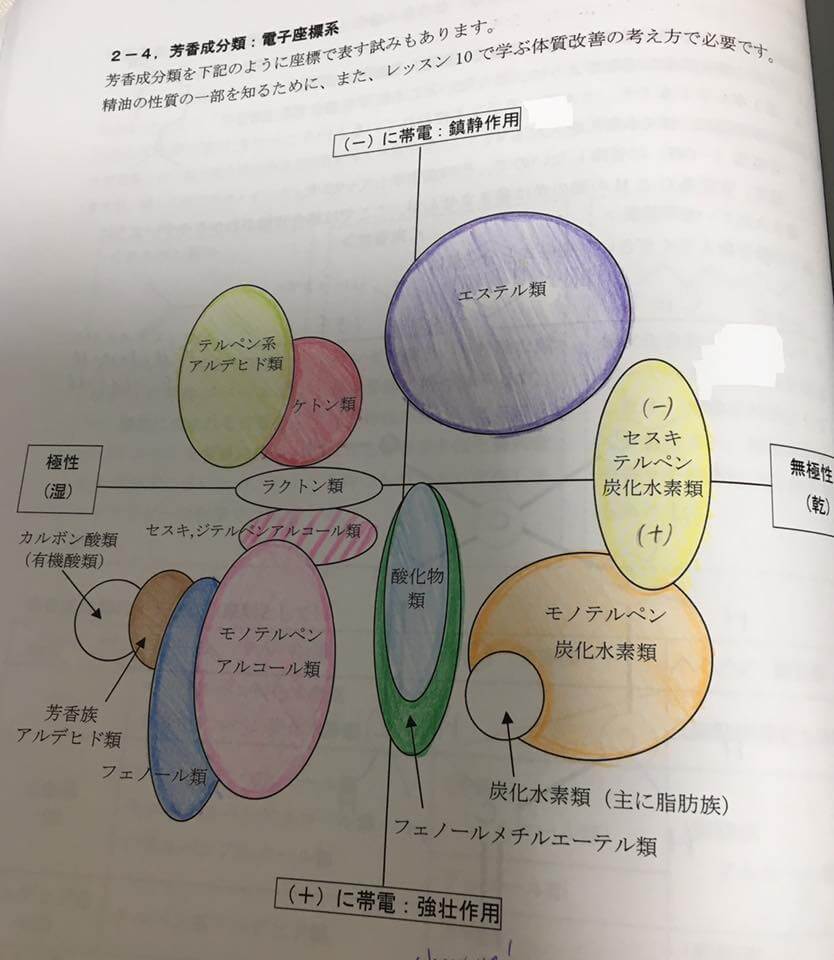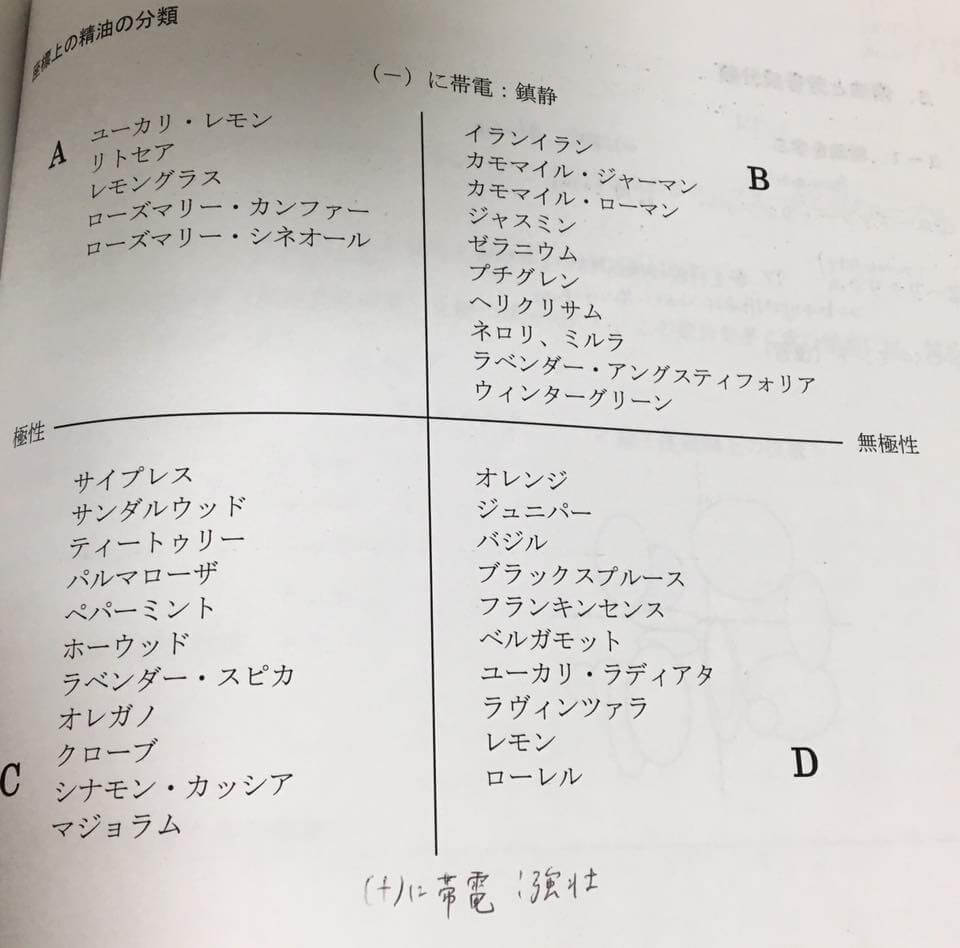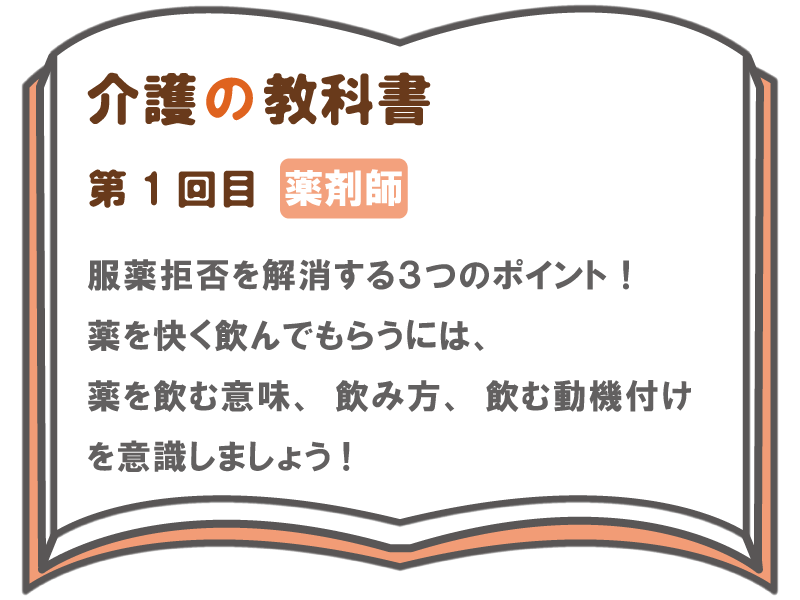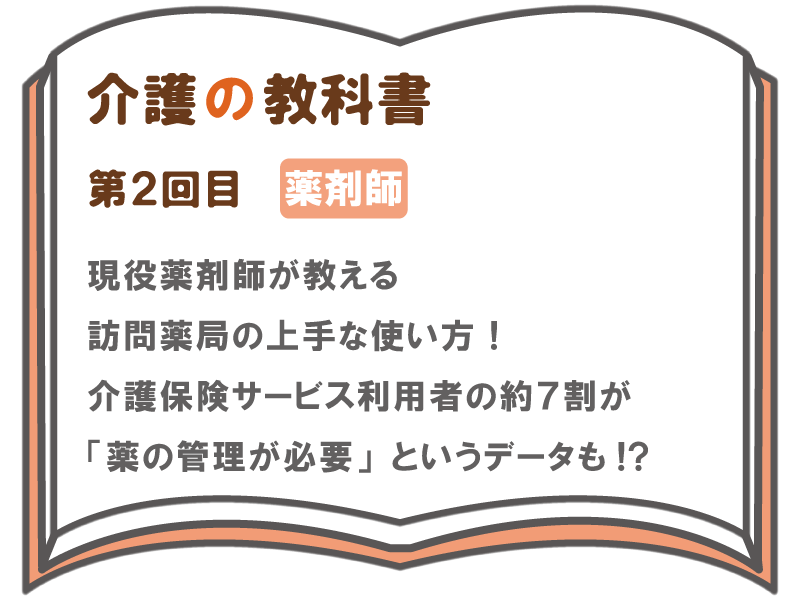【上高田勉強会共有】
2014年5月に販売開始された去勢抵抗性前立腺癌に対するイクスタンジ(エンザルタミド)カプセルについて、上高田店にて取り扱いがあり、勉強会開催がありましたので内容共有いたします。
■イクスタンジカプセル40mg
アンドロゲン受容体のシグナル伝達阻害作用を有する新規抗アンドロゲン剤
【適応:去勢抵抗性前立腺癌(CRPC)】
→ホルモン療法が効かなくなっている状態
→イクスタンジ導入時期
→アンドロゲン除去療法(以下、ADT)施行後PSAが最低値(nadir)から25%以上かつ上昇幅として2ng/mL以上で患者への説明を開始
【イクスタンジの特徴(一般)】
・1日4カプセル(160mg/日)の服用が必要(何カプセル剤で長径21mmと大きい)
(→現在、錠剤への製剤化を試みている段階とのこと)
・発現頻度の高い副作用は疲労・倦怠感、悪心、食欲減退
(→化学療法と異なり、生化学的用量制限毒性が少ない)
・国際共同第Ⅲ相試験(PREVAIL試験)においてプラセボ群と比較し、OSを有意に延長し、死亡のリスクを29%低下させた(Kaplan-Meier法)
・PREVAIL試験においてプラセボ群に比べPSFを有意に延長し、画像診断上の病勢進行および死亡のリスクを81%低下した。
・1カプセル 2354.10円であり、一カ月当たり28万円ほどの費用がかかる
(→高額療養費適応)。
・ワーファリンとの相互作用があるため、抗血栓薬を使用する場合は腎排泄型のプラザキサ等への変更が必要
【イクスタンジの特徴(他剤比較)】
・食事の影響を受けない
・ステロイド併用の必要がなく、ステロイドによる副作用に制限されることがない
(→糖尿病を合併した患者さんにも使用可、骨粗しょう症の副作用がない)
・治療選択としてビカルタミドの代替となりえるポディショニング
(→OS延長のデータが他剤になく単純比較はできない)
【薬剤師としてできること】
・有用性の確認された用量での服用を継続できるよう、副作用の説明・管理
(CTCAE Grade2を呈する疲労、倦怠感、悪心・嘔吐、食欲不振発現時の治療コンサルタント)
・イクスタンジ治療抵抗性になった場合の次の治療の選択肢の共有
【感想】
・ホルモン依存性の癌種にはホルモン療法が著効し、化学療法で見られる血液毒性の頻度が低いことが特徴であることが分かった。特にイクスタンジの用量制限毒性は患者の主観的な事象も多く、薬剤師も治療継続に大いに寄与できると感じた。
・同種同効薬のある新薬は、承認取得のためには既存薬に勝るポイント(有効性、副作用の発現率低下、低コスト)が必要となる。イクスタンジは実臨床での使用成績を蓄積の上で更なるエビデンスが構築されると考えられる。
・地域の薬剤師は前立腺がんの1つのマーカーであるPSAのスクリーニングを早期に実施するよう健康な方への予防啓発で前立腺がんの早期発見、予防に寄与できる立場であると感じた。