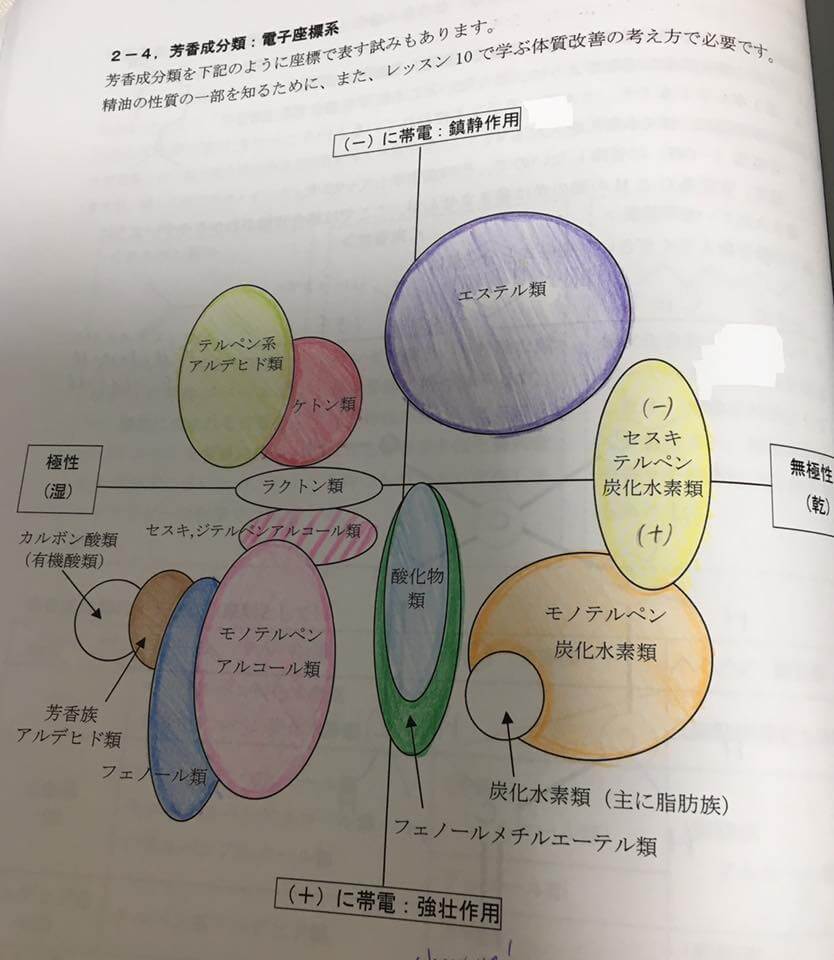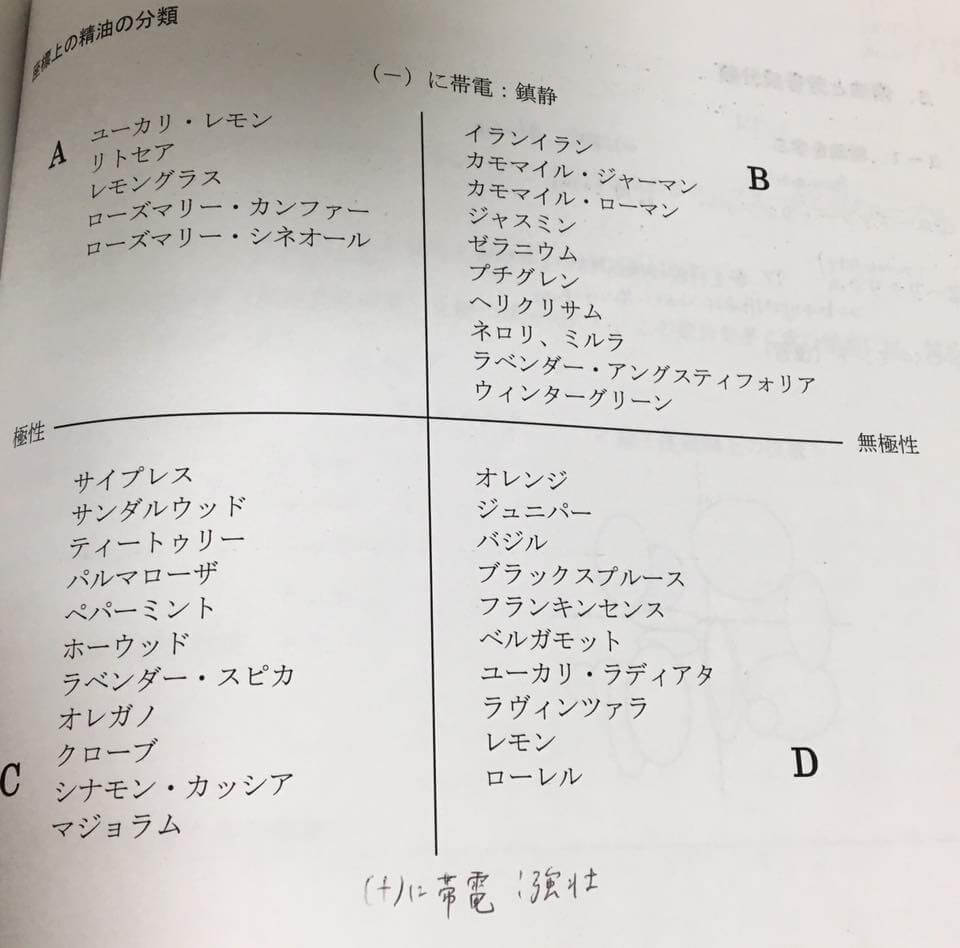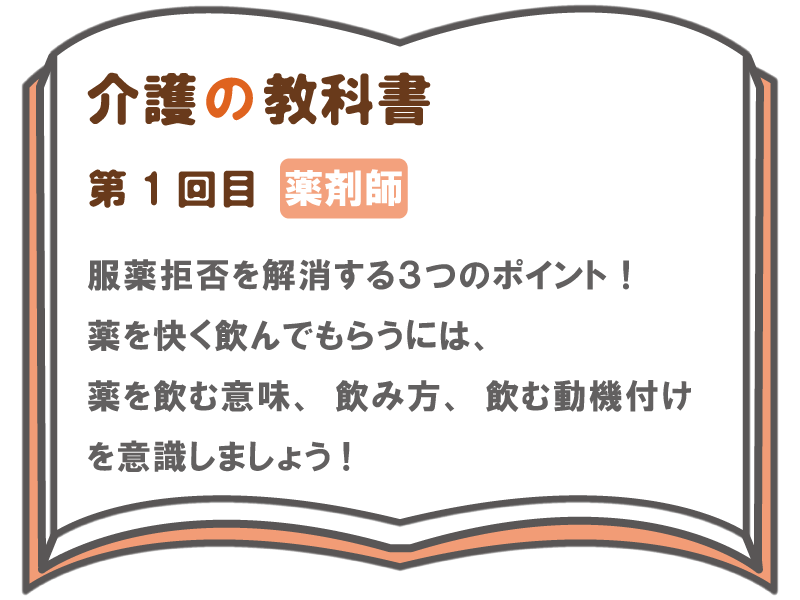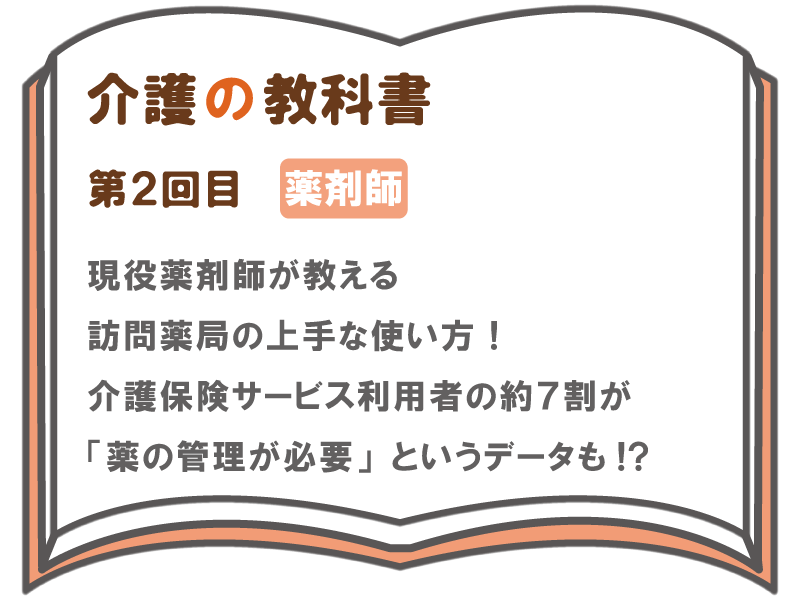《2月度(1/21〜2/20)分プレアボイド報告》
●本店より4件●
①前回メルカゾール5mg 6T/2×朝夕食後でお渡しした方が、今回4T/2×となっていたため、服薬指導時に「朝夕食後のまま、1回の錠数が3錠から2錠に変わって、1日計4錠に減ったのですね。」とお話ししたところ、「前回受け取った翌日に先生から直接電話があって、1日1回朝だけ2錠にするように言われたので、今は朝の2錠だけ飲んでいます。
これだと夕も2錠で増えちゃうので、ホルモンの値は良くなってるって言ってたからおかしい。」と返答あり。
→処方医へ上記経緯をお伝えして確認したところ、2T/1×朝食後(現在の用法用量で継続)に変更となった。
②いつもFAXで処方箋を受け付け、郵送の方。
前回 六君子湯の処方がなかったため本人に電話で確認し、「飲むと気持ち悪くなってしまうから、処方をやめてくれと自分から先生に伝えた。」との回答を得ていたが、今回六君子湯も処方されていたため、再度本人へ確認。
再開を頼んだ覚えはないとのことで、処方医へ問い合わせ。
→六君子湯は処方削除となった。
③かかりつけ(耳鼻科ではない)のいつもの処方に、ナゾネックス点鼻液56μg112噴霧 1日1回1噴霧 が追加されていた。
症状はかなり軽度のようではあったが、患者様は大人の方であり、本剤は12歳以上では通常1日1回各鼻腔に2噴霧ずつであるため、処方元へ問い合わせ。
→1日1回各鼻腔に2噴霧ずつの指示に変更となった。
●患者様曰く、今回の医師がお薬手帳を見て、「1年前に他で処方されているのと同じ薬を出しておきます」と言っていたとのこと。
その1年前の他院処方(当局でお渡ししたようだったためPC画面で確認したところ)は「1日1回」であり、何噴霧ずつかの詳細指示がないものでした。
④ムコダイン錠250mg 2T/1×朝食後の処方。
→9歳であり、1日量は問題ないが、1回量は多いこと、そもそも通常分1の薬ではないため、確認のため医師へ問い合わせたところ、2×朝夕食後に変更となった。
●通常1日3回の薬であり、小児では保育園・幼稚園・小学校に通園・通学中の昼は飲めないこともあるだろうと考慮して医師が1日2回で処方することはよくあるものの、1日1回は疑わしかったため、問い合わせに至りました。
●西荻店より7件●
①タリビッド錠100mg 1T/1× 5日分との処方を受けたが、通常300〜600mg/2〜3×の薬剤であるため投与量・回数が少なく、減量を要するような疾患の既往もない患者だったため、問い合わせ。
→薬剤間違いであり、クラビット錠500mg 1T/1× 5日分に変更となった。
②ホスミシン錠500mg 6T/日処方だったが、家族との会話から嚥下困難(+)と発覚。
家族からの希望もあり、剤形変更が必要と思われた。
ホスミシンDSは40% 1g/包の分包品在庫があり、3000mgは端数が出てまき直しが必要になるため、量的な点もあわせて問い合わせ。
→ホスミシンDS400 6g(2400mg)/日に変更となった。
③パキシルCR錠25mg 1.5T/1×処方。
CR錠にて割ることは不可であるため、問い合わせ。
→パキシルCR錠25mg,パキシルCR錠12.5mg 各1T/1×に変更となった。
●CR(Controlled Release)=放出制御、つまり徐放 設計されているため、割ったり粉砕したりするとその徐放機能が破綻してしまいます。
④1歳の小児にペリアクチンシロップ4mLとアスベリンDS7gで処方。
アスベリンDS7gは成人でも多い量であり、問い合わせ。
→アスベリンシロップ7mLに変更となった。
(1歳に7mLも多いですが、どうやら体格の大きいお子さんのようです。)
⑤元々イフェクサーSR150mg/日服用中の方に、今回追加で150mg/日の処方が出た。
上限量225mgの薬剤であり、今回の処方で300mg/日となるため問い合わせ。
→追加分は75mg/日(計225mg/日)に変更となった。
●本剤は上限量の他に増量の仕方も添付文書に記載があります。
「成人にはベンラファキシンとして1日37.5mgを初期用量とし、1週後より1日75mgを1日1回食後に経口投与する。なお、年齢、症状に応じ1日225mgを超えない範囲で適宜増減するが、増量は1週間以上の間隔をあけて1日用量として75mgずつ行うこと。」
⑥レクサプロ10mg 1T→1.5T/1×夕食後に増量となった方。
増量の旨確認しつつ服薬指導を行なっていたところ、「『増量時に気持ち悪くなるといけないから、その対策のお薬を出しておきます』と先生が言っていたのですが…他にお薬出ていないですよね?」と申し出あり。
→処方元に上記旨を報告・問い合わせし、ガスモチン5mg 1T/1×夕食後 14日分 処方追加となった(お渡しはGE)。
⑦レクサプロ10mg 1T/1×夕食後 25日分のみの処方、お薬手帳持参なしの方。
前回1月末に胃もたれの臨時処方で久し振りに来局されたようだが、メンタル系ではH27.10月に他の医療機関よりルーラン4mg 1T/2×朝夕食後 14日分 という処方が当局履歴上最後だったため、レクサプロは現在服用中の薬剤なのか お渡し時に本人へ確認したところ、現在服用中だが、一緒に処方依頼したレキソタンは処方が出ていないのかと質問あり。
規格・用法用量等詳細情報は本人から得られず、それも含めて処方元へ問い合わせ。
→レキソタン1mg 1T/1×朝食後 28日分 処方追加となった(お渡しはGE)。