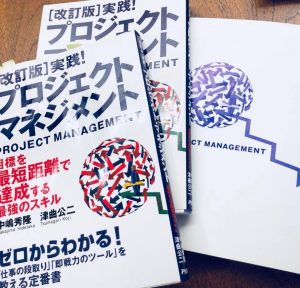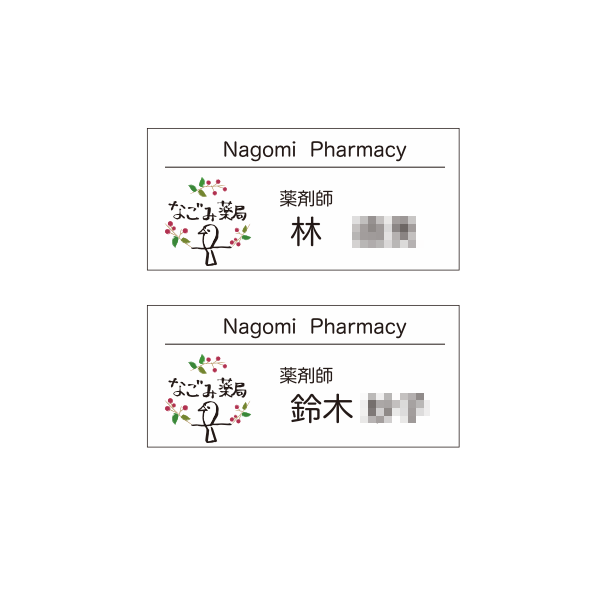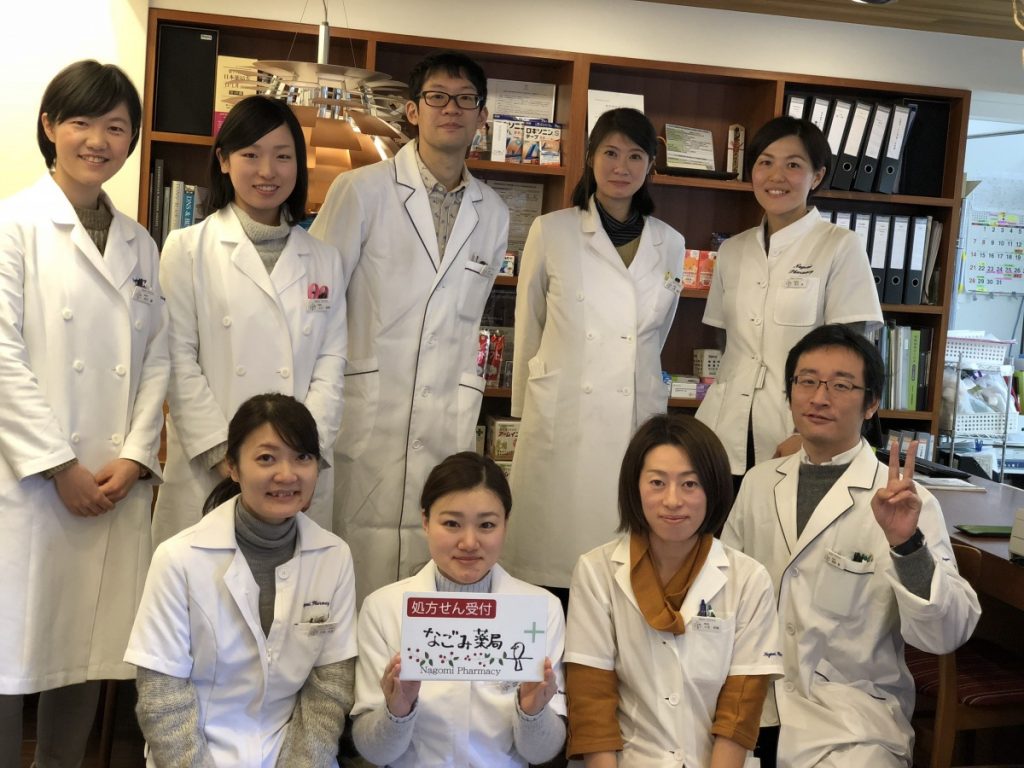妊婦・授乳婦の薬物療法について vol.1 『基本の考え方』
H30.3.27 なごみ薬剤師 K
なごみ薬局に入る前、病院の産科病棟担当薬剤師として2年間働いていました。そこで学んだ知識を少しずつではありますが共有させていただきたいと思います。語るにはボリュームが多すぎるので、勉強会を行うというのではなく、この場に少しずつアップしていきたいと思います。長々書くと、読む側も書く側も負担になるので…1ページに収まる程度でさらっと読みやすくお伝えできたらと思います。
週1以上のペースを目標にアップしていきます。
まず初回は基本の考え方について書きました。今後は具体的な内容について取り上げる予定です。(例えば、インフルエンザについてや喘息、便秘についてなどなど)取り上げて欲しい分野などがあればご意見をお待ちしています。
それでは、お付き合いのほどよろしくお願いします。
妊婦、授乳婦の薬物療法はとても奥が深く、やりがいのある領域です。また 遭遇するケースは多くはありませんが、薬局薬剤師としても必要な知識です。 しかし、単純に○×では評価できなかったり、データが少なかったりと、なかなか難しい領域でもあります。
そこで、わずかな知識ではありますが、今まで私が学んだことをここで少しずつ共有できればと思います。
【基本の考え方】
『より安全な薬剤を必要最小限に』
・ 禁忌は避ける
・ 内服(全身投与)より、外用(局所投与)を優先する
・ データがより多く、安全と考えられる薬剤を選ぶ
※例外もあります。 “より安全な”という部分の判断が現行の添付文書からできるかというと、 できません。多くは「有益性投与」と書かれ、安全性の比較はし難いです。 では、比較するためのデータが全くないかというと、そういうわけでもありません。
以下のような安全性を評価するための情報源を用いて、個々の状況に応じた判断をしていく必要があります。
それぞれの情報源によって、記載のある薬剤、ない薬剤が異なりますし、 多少評価に差がある部分もありますので、総合的に判断する必要があります。
【情報源】
わかりやすく、使いやすいものを紹介します。
・薬物治療コンサルテーション 妊娠と授乳 改訂2版(南山堂)
・実践 妊娠と薬 第2版(じほう)※本店にあります
・ 母乳とくすりハンドブック 2010
http://www.oitaog.jp/syoko/binyutokusuri.pdf
・ LactMed(※英語表記 アプリが便利です)